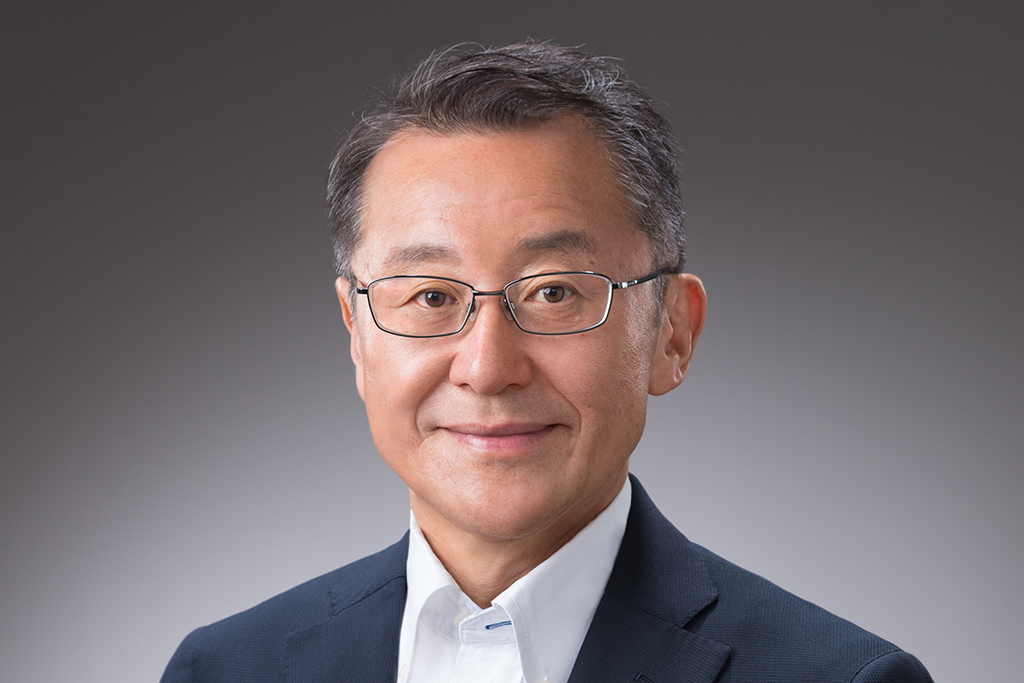

開志専門職大学
先生がこれまでマサチューセッツ工科大学(以下MIT)でどのようなことをされてきたのかを教えてください。
宮川繁
二つあります。まず、オンライン教育の仕事で、2000年からMITで使用されている教材をオンラインで公開する「オープンコースウエア(ocw.mit.edu)」のプロジェクトに携わりました。


開志専門職大学
誰でも講義に使用されている教材がオンラインで見られるということですか?
宮川繁
そうです。当時、そのMITの活動は、他の大学が利益を重視してオンラインのプログラムからお金を取ろうとしている動きから全く逆をいくものでした。

宮川繁
私としては、誰でも無料で見られることにすることで、注目されるのか、それとも無視されるのか分かりませんでしたが、良い教材を多くの人に見てほしいという気持ちでした。


開志専門職大学
その結果、どうなったのですか?
宮川繁
22年前にプロジェクトに着手した「オープンコースウエア」の利用者は、現在1億人に達しています。うれしいことです。多くの人に勉強する機会を提供したことができたと、手応えを感じています。


開志専門職大学
本当に誰でも無料で見ることができるのですか?
宮川繁
そうです。ヨーロッパ、アフリカ、日本からも多くの人がアクセスしています。誰でもMITの2500もの科目の教材にアクセスできます。サイエンス、エンジニアリング、人文系、ビジネス系、MITで教えている内容が見られるのです。

宮川繁
これによって、大学の教材は世界の人々に共有されるべきだという概念が確立されました。その動きを生み出せたことに誇りを感じています。


開志専門職大学
学びたい人はどこからでも自由に学べるということですね。素晴らしいことだと思います。
宮川繁
それからもう一つのお話したい実績は、私の専門の言語学の分野のことです。実は先日、ブラジルのサンパウロ州研究財団からサンパウロ・エクセレンス・チェアという名誉ある賞を受賞しました。


開志専門職大学
どのような理由で受賞されたのですか?
宮川繁
私の「言語と進化」をテーマにした研究内容に対しての表彰でした。


開志専門職大学
言語を進化論という意味合いで研究するということですか?
宮川繁
はい。進化の過程で言語はどんな形で発展していったのか、ということですね。そして、私は人間しか持っていない言語は、もともと何百万年以上も前から存在していた鳥のさえずりと、猿のコミュニケーションのシステムがうまく組み合わさってできたものなのだと仮定しました。

宮川繁
これに関してはイギリスのBBCのラジオ4チャンネルでも特別プログラムが放送されました。


開志専門職大学
その研究に対して賞を授与したのですね。
宮川繁
私自身も2022年4月よりサンパウロ大学の客員教授に就任し、その研究をMITと同様に、サンパウロ大学でも発展させるために尽力していきます。


開志専門職大学
それではアメリカだけでなく、ブラジルにも頻繁に訪れることになるのですね?
宮川繁
楽しみです。ブラジルは本当に楽しい国です。食べ物がおいしくて人が温かい。しかも、世界の中で日系人が最も暮らす国です。だから、僕が街を歩いていると、現地の人間だと間違われてポルトガル語で話しかけられます。


開志専門職大学
ブラジルで、宮川先生にとってまた新しいページが始まるのですね。さて、言語学を専門にされた最初のきっかけを教えてください。
宮川繁
これは私が国際基督教大学の3年生だった時に、井上和子先生という非常に高明な言語学者の講義を受けて、その内容と講義の方法に感銘を受けたからなんです。

宮川繁
井上先生は、世界には数多くの言語、7000くらいの言語があるけれども、その根本は同じであり、普遍的なシステムが存在するというノーム・チョムスキー教授(アメリカの言語学者)のメソッドを非常に熱意をもって教えてくださいました。


開志専門職大学
世界中にある、いろいろな言語は全く別のものではなく、関連性が認められるということですか?
宮川繁
そうなんです。いろんな人間がいるけれども、同じ人間なんだという思想ですよね。その奥深さに感動しました。

宮川繁
しかも、そのチョムスキー教授はMITに所属されていたので(現在はMIT名誉教授)、私もこうして教授と同じ学部で、しかもオフィスも隣だったのでお世話になり、大変親切にしていただきました。夢のようでした。まさに、物理学の学者がアインシュタインと一緒に働くことができたというような、そういう経験でした。


開志専門職大学
言語学に携わるきっかけとなった「生きる伝説」と同じ大学で働けたとは、素晴らしいですね。でも、それも宮川先生が日本国内に留まらずに、海外に出たからこそ実現したことですよね。
宮川繁
そうですね。日本人にとって海外で仕事をするということは非常に重要です。まず、それによって日本という国を客観的に見られるようになります。

宮川繁
日本国内にいると、日本の良さを客観的に捉えることが難しく、なんでも当たり前だと思ってしまいます。しかし、一度海外に出て、日本を振り返ることで日本の良さが見えてきます。


開志専門職大学
具体的にはどのような点ですか?
宮川繁
日本人は何て丁寧で、そして誠実な国民なのかということです。そして、自分の国に感謝の気持ちが生まれるはずです。

宮川繁
さらに、日本にいると、自分と他者とを切り離して考えることをしません。でも、海外に出ることで周りが日本人ではないということで、自分自身を他者と切り離して考えることを始めると、そこで初めて自分自身を理解します。


開志専門職大学
日本の中にいると自分自身を見つめることが難しい、ということですね。
宮川繁
自分を客観的に見つめることで自己が確立するのです。あとはやはり、グローバルな社会の中で問題を解決するためには、多様な視点を養うことが重要です。そのためにも海外に出ることをお勧めします。でも、とにかく海外で認められるには、日本人はもっと発言しなければいけません。


開志専門職大学
先生の講義でも日本人は発言が少ないんですか?
宮川繁
そうなのです。もっと手を挙げて、意見を主張してほしいですね。


開志専門職大学
どうして日本の学生は積極的に発言できないのでしょうか?
宮川繁
小学校の時からそういう、受け身な教育を受けていることも一因でしょうね。他方、韓国や中国の学生はよく発言します。インド人の学生は「もう勘弁して」と言いたくなるくらい、ずっとしゃべっています(笑)。だから、教育のせいだけでなく、国民性というものもあると思います。

宮川繁
日本人は皆が静かだから、その中にいると自分も静かになってしまいます。人間は周囲の影響を非常に受けやすいですからね。海外の人から「日本人はおとなしい」というステレオタイプで見られていますよ。


開志専門職大学
日本人が意見を言えるようになるためには、一度海外に出てみないと、そういう風に見られていることも実感できないということでしょうか?
宮川繁
ちなみに、私は会議では一番先に手を挙げます。声も意識的に大きくしています(笑)。


開志専門職大学
宮川先生は自らの行動で、「全員の日本人がおとなしいいわけではない」とアピールしているんですね。さて、次に、これから大学に入る人たちに学生時代に経験しておくべきことをアドバイスしていただけますか?
宮川繁
アドバイスは二つあります。まず、視野を広げる努力をしてください。日本の中にいると、一定の視野のままでも快適に暮らせるので視野が広がりません。でも、今はグローバルな時代です。たとえ自分が海外に出なくても、日本にいても、どんどん外国人が日本に入ってきます。

宮川繁
これからの時代に適応するために視野を広げる一番の方法は、やはり一度は外国に出て行くことですね。外国の異文化に接して、現地の人と交流してください。そして、視野を広げるだけでなく、先ほども言ったように、日本や自分自身を客観的に見ることで日本人とはどんな国民か、自分はどんな人間かということを確立してほしいです。

宮川繁
さらに、外国の人から日本について聞かれるはずです。その時にはきちんと日本について伝えられるように知識を身に付けておくことが大事です。


開志専門職大学
二つ目のアドバイスは何でしょうか?
宮川繁
学び方を身に付けてほしいということです。世の中の情報や知識はすごいスピードで増え続けています。今、習得している知識も、あと5年もすればものにならないくらい、入れ替わりが激しくなっているのです。ですから、常に新しい知識を学び続けることが求められます。


開志専門職大学
学びを止めてはいけないということですね。
宮川繁
最近の研究では、これからの社会人は仕事をしながら、年100日以上勉強をしないといけないというデータも出ています。


開志専門職大学
時代に取り残されないために、ずっと勉強を続けないと働くこともできない?
宮川繁
そうです。ですから学生の間に、社会人になってからも学び続けることを見越して、「学ぶ力」を身に付けておいていただきたいと思います。


開志専門職大学
そのためにはどうしたらいいのでしょうか?
宮川繁
一つの方法は、インターネットを活用することです。私が手がけたオープンコースウエアに留まらず、オンライン上に学びの機会を数多く見付けることができます。


開志専門職大学
さて、今後の宮川先生のお仕事の上での目標をお聞かせください。
宮川繁
まずは、今後、どのようにすればより良い社会を創り出せるのかを真剣に考え、そのためにできることをしていきたいです。


開志専門職大学
具体的にはどういうことですか?
宮川繁
コロナ禍で社会の皆さんがテレワークという働き方に慣れました。一方で規制が緩和されて、人々がオフィスに戻るようにもなっていますが、コロナ禍前と同じ状態には戻りません。なぜなら、強制的に以前と同じ働き方に戻そうとすると、テレワークに慣れた人々から不満が出ることは明白だからです。ですから、これからの職場や働き方をどのようにしていくべきかを、考えていきたいですね。


開志専門職大学
言語学者としての究極の目標は何ですか?
宮川繁
人間の言語がどのような形で進化してきたのかについて、有名なチャールズ・ダーウィンの仮説が正しいということを私が証明したいと思います。


開志専門職大学
あの有名な「進化論」ですね。ぜひ、証明してください。楽しみです。では最後に、開志専門職大学の特別講義で宮川先生がどのようなことについてお話しいただけるのかを少し教えてください。
宮川繁
まずは職場の将来や働き方がどうなるかについてお話しします。これに関しては、私が携わっているオンライン教育にもつなげてご紹介します。さらに、私の言語学の研究内容についても話したいですね。


開志専門職大学
盛りだくさんな内容ですね。それではどうぞよろしくお願い致します。
特別講師 宮川繁氏
マサチューセッツ工科大学言語学教授
マサチューセッツ工科大学(MIT)言語学教授。10歳でアメリカに渡り、ノースカロライナとアラバマで過ごした後、20歳で帰国。国際基督教大学を卒業後に東京のアメリカンスクール・イン・ジャパンの教員を務めた後再渡米し、アリゾナ大学博士課程を修了。オハイオ州立大学教授を経て、1991年、MITの理論言語学の教授就任。日本語、英語をもとに統語論の研究に携わる。2000年からMITの講義内容をインターネットで配信する公開オンライン講座、オープンコースウエアの企画運営に関わる。
インタビュー:福田恵子




