脚本/プロデュース領域
脚本/プロデュース領域 授業を支える先生たち
教授(脚本・企画・プロデュース分野長)
村井 さだゆき
MURAI Sadayuki
担当科目
物語概論/脚本分析実習/近代世界観研究


「幾何学を知らざる者、この門をくぐるべからず」
アカデミーとは、古代ギリシアの哲学者プラトンがアテネ郊外に作った学園、アカデメイアを語源とする言葉です。その入口にはこう書かれていたそうです。
プラトンにとって幾何学は真理と同義でした。ものごとを深く探究する意思のない者はこの学園で学ぶ資格はないという意味ですね。時代が下ってルネサンス期、ラファエロはこの学堂を題材に一枚の壁画を残しました。
そこには、同時代の錚々たる芸術家たちが、古代の哲学者たちになぞらえて描かれています。レオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロ、そしてラファエロ自身も。フィレンツェやローマにつどった彼らは、お互いに競争し、刺激を与え合い、数々の傑作を生みました。その意気や、プラトンのアカデメイアにつどった哲学者たちと何ら変わらなかったでしょう。
彼らもまた、それぞれに芸術の真理を探究していたのです。私たちのアニメ・マンガ学部も、そのような場でありたいと願っています。アニメやマンガは、現代視覚文化を代表する新しい芸術分野です。そこには学ぶべき理論や法則が山のようにあります。それらを学び、問い、自らをこの分野の高みに押し上げたいと願う人に、このふるまちアカデミーの門をくぐって欲しいと思います。
教授
成田 兵衛
NARITA Hyoe
担当科目
コンテンツビジネス概論/マンガ産業論/企画プロデュースゼミ
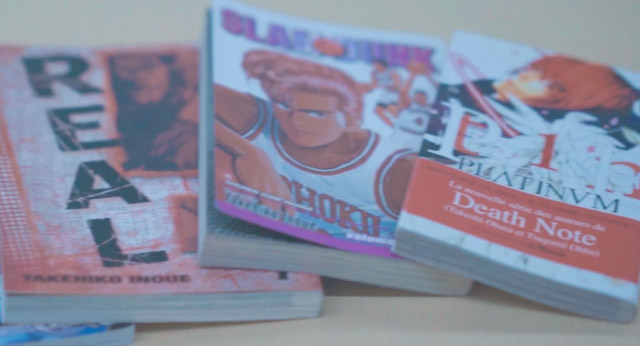
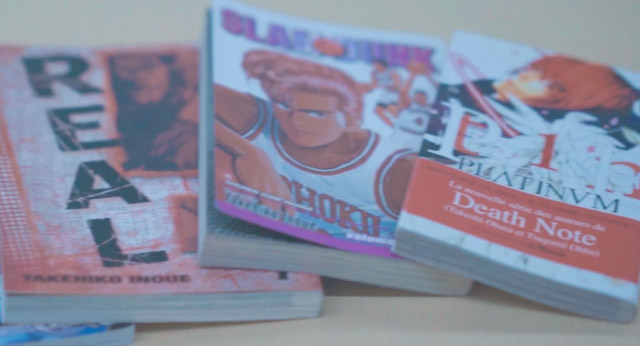
「リアル」「スラムダンク」「プラチナエンド」
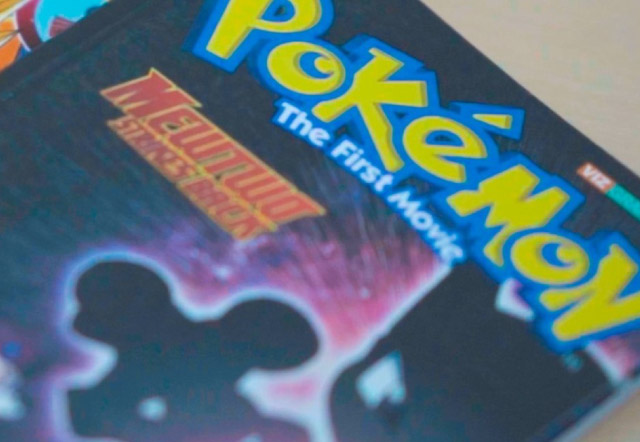
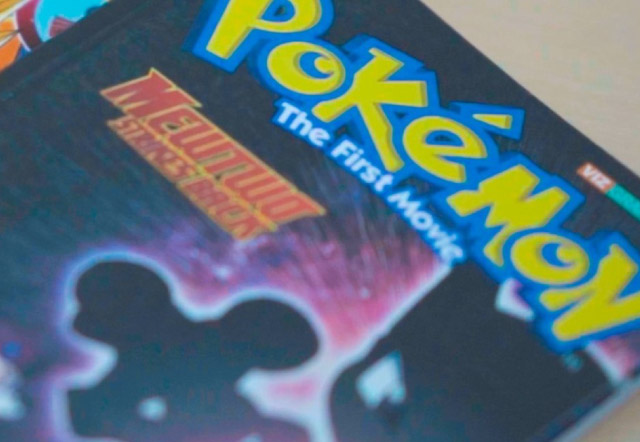
「ポケモン」


「ドラゴンボール」
国際競争力を身につけるためには企画力とプロデュース力が必須
「日本にディズニーランドがあるんだから、海外にマンガランドがあってもいいじゃないか!」そう言い続けて25年が経ちました。しかしいまだに実現化されていません。なぜか? ひとことで言うと、作品や分野の持つポテンシャルを国際的に最大化するための企画力やプロデュース力が、外国人に比べて弱いからです。しかしその力は一朝一夕には身につかず、学習と実践の積み重ねがあって初めて培われるもの。
“アニメ・マンガ・映画・ゲーム…、なくてもいいけど、あると世界中がうれしい!”
海外ではアニメもマンガも人気ですが、日本ほどではありません。「マンガ」「アニメ」という単語を知っている日本人が人口の80%以上だとすると、海外では多く見積もってもせいぜい20%〜30%。ただ、20年前は間違いなくひと桁%でした。皆さんが世に出る数年後、あるいは10年後、20年後のマンガ・アニメの海外知名度を想像すると、今からワクワクします。そんな素敵な未来を信じて本学の教員になりました。「あきらめたらそこで試合終了ですよ」。スラムダンクの安西先生の言葉を座右の銘に、変化の時代、皆さんとともに忖度抜きで立ち向かっていければ幸せです。


准教授
野上勇人
NOGAMI Hayato
担当科目
キャリアデザインⅢ/パブリッシング実習Ⅰ・Ⅱ/印刷・広告実習Ⅰ・Ⅱ

国際マンガ産業論
自分たちが制作したマンガやアニメが、国内に限らず海外でどのように展開されて読者や視聴者の目に触れるのか?メディアミックスはどのように行われるのか?商業マンガを目指すのであれば最低限は知っておきたい知識を身につけ、さらに新しい方法も一緒に探していきましょう!
物語記号学
アニメやマンガは「物語」を伝えるメディアです。すべての芸術がそうであるように、「物語」もまた、記号を使って伝達されます。20世紀に入って、記号についての考え方は大きく変わりました。記号学の誕生です。この講義では、比較的新しい学問である記号学の考え方を使って、さまざまな「物語」の背後に潜む構造を、ていねいに解き明かしていきます。
表象芸術論
それぞれの専門家たちによるオムニバス講義。マンガ・アニメ作品はある世界観に基づき、キャラクターと物語を縦横の糸として編み上げていく作業ですが、それを絵として具体的に表現しなくてはなりません。人物には何を着せるか、背景には何を描くか─服装や化粧のドレスコード、背景に描かれる建築的空間、工業製品などの記号性について考えます。
近代世界観研究
「世界観」とはなんでしょう?勇者が魔王と戦う世界、吸血鬼が夜の街を跋扈している世界、あるいは探偵と怪盗が知恵比べをしている世界etc. これらすべてが、それぞれの作品の「世界観」だと言われます。こうした「世界観」はどうして生まれたのか。私たちはなぜそれを面白いと思うのか。アニメやマンガに必ず必要とされる「世界観」について一緒に考える授業です。







