教員紹介
-
実務家教員

事業創造学部
向 正道 教授(学部長)
MUKAI Masamichi
担当科目
デジタル経営
AI、クラウド、モバイル等の代表的なデジタル技術と活用方法、また各産業がどのようにデジタル化を進めているかを学修します。
デジタルマーケティング
マーケティングの基本事項である製品、価格設定、販売チャネル、プロモーションについて、実際のオンライン店舗の運営におけるWebマーケティング戦略立案のための各種分析方法などを学ぶ。
実践デジタルサービス企画
スマフォアプリを代表例として、デジタルサービスの事例分析、及び企画までの実践的手法について、演習を通じて学修します。
京都大学工学研究科原子核工学専攻 修了。早稲田大学商学研究科博士後期課程 修了 博士(商学)。 新日本製鐵株式会社入社。新日鉄ソリューションズ株式会社(現 日鉄ソリューションズ)にて、コンサル部門、人事部門の要職を歴任。
-

事業創造学部
德田 賢二 教授(副学長)
TOKUDA Kenji
担当科目
流通論の基礎と応用
生産から小売業までの消費プロセスの中で流通を捉え、商業の概念、商業構造の変化、製造業者と商業の関係について、マーケティングの理論と関連させて学ぶ
地域経済産業論
地域の視点から見た日本経済を経済面、産業面、さらに企業視点から学ぶ
一橋大経済学部卒業。日本長期信用銀行本部、融資、調査部等を経て、専修大学経済学部教授、同大大学院経済学研究科長、法人評議員等歴任、名誉教授就任。
-
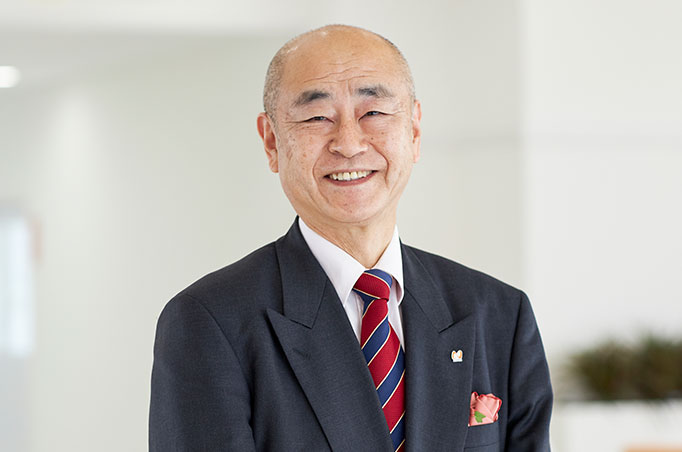
事業創造学部
櫻井 繁樹 教授
SAKURAI Shigeki
経済産業省にて産業技術・エネルギー政策の策定、文部科学省にて教育研究政策の策定、京都大学大学院総合生存学館教授歴任。
-
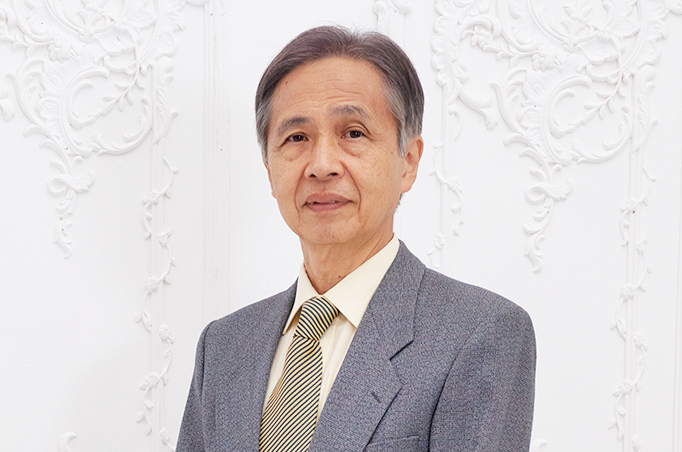
事業創造学部
近藤 正幸 教授
KONDO Masayuki
担当科目
イノベーションマネジメント
イノベーションの必要性の理解と、イノベーションをマネジメントする上で必要な知見の修得を目指して、オープンイノベーションを含め、企業の研究開発、技術開発及び上市・普及に関する知識やマネジメントの方法を学修する。
トップランナー研究
産業界において先進の取り組みを実践している事例についての考察・研究を通じ、専門職業人としての心構え、考え方、行動指針等を理解し、自己の職業観確立のための一助とすると共に、思考力、判断力、実践力の向上を目指す
経済学の基礎
ミクロ経済学については、市場における需要と供給を通じた個人・消費者や企業の意思決定・行動、外部経済・外部不経済などについて学修する。マクロ経済学については、国内所得(GDP)等の概念や、経済政策、経済成長、国際経済等について学修する。
スタンフォード大学大学院修了。通商産業省(現経済産業省)、世界銀行、英国王立国際問題研究所、文部科学省科学技術政策研究所(現科学技術・学術政策研究所)、横浜国立大学大学院などで勤務。横浜国立大学名誉教授。博士(学術)。
-
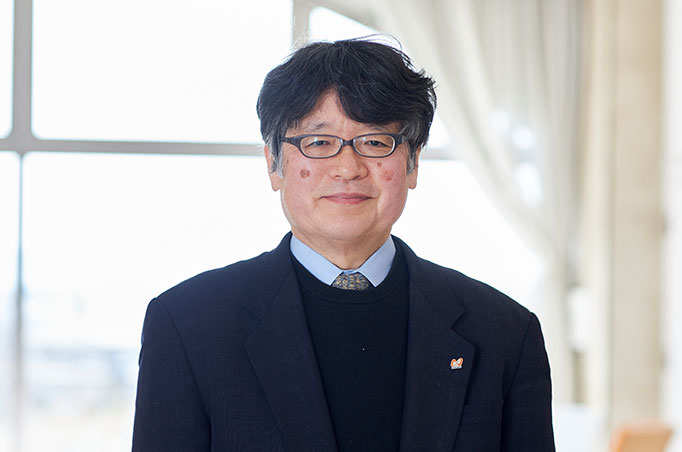
事業創造学部
西村 伸也 教授
NISHIMURA Shinya
担当科目
企業内実習Ⅰ
実際の企業現場で業務を体験することで信頼関係を築くことの重要性を理解し、また社会人としての身だしなみ・マナーについてもその能力と態度を身に付ける。
地域資源活用実習
フィールドワークの手法を修得し、地域資源活用の手法を知識と実践により理解する。
地域産業研究Ⅶ
新潟県におけるまちづくりの動向や現状の課題について具体的な事例を通して理解し、魅力あるまちづくりのためのアイデアの考案や方策について考える。
東京大学卒業・工学博士。建築計画デザイン・設計方法が専門。主に学校建築のデザインと実践的なまちづくりに携わる。
-
実務家教員

事業創造学部
古屋 光俊 教授
FURUYA Mitsutoshi
担当科目
ビジネスプランの基礎
ビジネスプランの作成およびプレゼンテーションに関する基本的な知識を学び、実現可能な事業計画を作成する
ビジネスプランの応用
経営者・起業家として必要となる基本的スキルや発想法と、ビジネスプランをより具体的なアイデアに発展させる事業計画策定の方法を学ぶ
実践ベンチャービジネス
起業家にとって重要となるベンチャー・ビジネスの基礎的事項・知識について学び、考察する
アントレプレナーシップ論
事例研究や技法解説を通じて、起業家に必要とされる資質や倫理観を学ぶ。
東京工業大学大学院、電子物理工学修士。早稲田大学大学院、博士(商学)。三菱商事、PwC、IBM、ベンチャー企業経営。九州大学客員教授(2023年3月まで)。RUFT株式会社代表、早稲田大学招聘研究員。
-

事業創造学部
星 和樹 教授
HOSHI Kazuki
担当科目
経営学の基礎
経営の基本的な事項といわれる、ひと、もの、金、情報の取り扱いを学ぶ
経営戦略論
経営戦略の本質と多角化戦略、国際化戦略、すきま戦略など具体的な戦略を学ぶ
ビジネスモデル研究
様々なビジネスモデルを取り上げ、具体的な事例を通じて経営知識・理論を学ぶ
基礎ゼミ
新潟県立新潟商業高等学校出身。愛知産業大学経営学部准教授歴任。
-
実務家教員

事業創造学部
増田 達夫 教授
MASUDA Tatsuo
担当科目
地域産業研究Ⅲ(環境)
環境問題の概要と国内、国外で進められてきた取り組みについて学び、環境問題が地域に及ぼすインパクトについて考える
国際動態論 (International Dynamics)
気候変動はじめ大規模な国際交渉の展開、主要な国際機関の機能、世界経済フォーラム(ダボス会議)の役割、有力な多国籍企業の戦略、石油資源をめぐるパワーゲームなどを学ぶ。講義も議論もすべて英語で行われる。
現代史と国際関係論
現状の国際関係と、これからの国際関係を理解する上で重要な世界的な歴史と日本の関わり、現在の日本が抱える国際的な課題を学ぶ
外務省、経済産業省、パリの国際エネルギー機関局長を経験。電子部品メーカーSOC役員、英国のFairCourt Capital社会長として活躍。ケンブリッジ大学歴史学部卒業。
-

事業創造学部
石川 秀才 教授
ISHIKAWA Hidetoshi
担当科目
ビジネス実務法務Ⅰ・Ⅱ
企業取引の法務(契約など)の基礎的な知識習得とともに、ビジネス実務法務における関係を理解する。
不動産法入門
不動産取引において必要な法律の知識を理解するとともに、不動産法の種類や構成など不動産法の全体像を理解する。
不動産取引演習
不動産取引を行うための基礎知識と実践力を体的な事例を基に学ぶ。
企業内実習Ⅰ
実際の企業現場で業務を体験。企業活動における協調性やビジネスマナーを学ぶ。実習先企業で業務やプレゼンテ-ションを体験し、地域産業の振興・活性化を推進する創造力と実践力を学ぶ。
特別講座(宅建)
宅地建物取引士試験の知識を理解し、資格取得を目指す。
明海大学不動産学部、日本大学理工学部まちづくり工学科を歴任。専門は、不動産法。中央大学、東京経済大学で宅地建物取引士資格試験の受験講座講師など、法律系の国家試験受験指導にも深くかかわる。
-
実務家教員

事業創造学部
赤木 徳顕 教授
AKAGI Tokuaki
担当科目
マーケティング
マーケティングの基本概念及び環境分析・戦略立案・施策立案の理論的フレームワークについて学ぶ。
会社設立実習Ⅱ
会社設立実習Ⅰで学修した事業計画、資金計画、経営(仮想)、決算、税務申告までの一連の流れの理解を踏まえ、学外での実際の会社設立を想定した具体的な計画を策定する。
実践的統計学
ビジネスに関係する国内所得や景気動向指数等の経済統計の成り立ちと見方、実際に統計を作成する際に必要となる標本設計等の基礎やビッグデータ等のデータを分析する統計分析手法を学ぶ。
企業内実習Ⅲ
実習先企業の事業内容、社会的役割を理解し、業務現場の見学やヒアリング、実際の業務体験を通して自社の事業状況、自社の強みや弱みを把握し、業界事情の分析、市場の分析、競合他社の分析、社会環境の分析を踏まえて、実習先企業の抱える課題を認識し、課題の解決のための方策を考察する。
事業開発実習
マサチューセッツ工科大学・経営大学院修了。野村総合研究所シリコンバレー法人のCFOを務めた後に、起業しその後、岩手大学で起業家育成講座、帝京大学でマーケティングおよびデータサイエンスを担当。
-
実務家教員

事業創造学部
小川 元也 准教授
OGAWA Motoya
担当科目
グローバル経営
グローバル展開の手法や戦略を企業の事例を取り上げながら考察し、異文化における市場戦略や組織マネジメントについて学ぶ。
広報戦略の実践
企業理念やブランドの体系を理解したうえで、社内外へのコミュニケーションの戦略と手法を学ぶ。
地域産業研究Ⅷ(カルチャー・エンタテイメント)
エンターテイメントビジネスの市場分析や事例研究を行い、各種エンターテイメントビジネスの国内・海外展開の戦略を考察する。
企業内実習Ⅱ
企業や自治体での実務を経験したうえで、マーケティング視点での企画を提案し、実行計画を策定する。
慶應義塾大学大学院経営管理研究科(MBA)修了。自動車業界、広告業界、エンターテインメント業界で勤務し、マーケティング、経営企画、グローバル戦略などを担当。2013年から5年間米国に駐在。
-
実務家教員

事業創造学部
福田 稔 准教授
FUKUDA Minoru
担当科目
企業内実習Ⅰ
実際の企業現場で業務を体験することで信頼関係を築くことの重要性を理解し、また社会人としての身だしなみ・マナーについてもその能力と態度を身に付ける。
実践企業革新
企業革新の必要性を実際の事例研究を通じて理解し、どのような手法で革新するか考察する。
会社設立実習
学生同士や担当教員とのディスカッションを繰り返しながらビジネスプランを策定し、実際に会社設立に必要な計画策定から実行まで実践的に学習する。
一般社団法人日本イノベーションマネジャー協会代表理事として、様々な機関・企業をサポート。近畿大学工学部非常勤講師、広島大学工学部客員准教授歴任、実務家としてイノベーションマネジャー®認定講座、UIターン創業相談・事業承継にも取り組んでいる。
-
実務家教員

事業創造学部
明珍 儀隆 准教授
MYOCHIN Yoshitaka
担当科目
会計学
企業の取引や経営実態を理解するうえで不可欠なビジネスの言語とも言われる会計学の全体概要を学ぶ。
財務諸表論
会社法、金融商品取引法などの会計諸規定、さらには国際会計基準(財務報告基準)をもとに、企業活動の成果の認識、測定及び開示に関する問題点、財務諸表における基本概念を学ぶ。
企業内実習Ⅲ
経営戦略や経営組織の理解、トップマネジメントの理解、会計・財務に関する理論を総合的に活用し、課題解決策を企画提案書にまとめ、プレゼンテーションを体験する。
新規商品開発・販売実習Ⅰ・Ⅱ
実習先企業での販売活動、課題分析、企画立案、プレゼン等で創造力と応用力を身に付ける。
トップランナー研究
産業界において先進の取り組みを実践している事例についての考察・研究を通じ、専門職業人としての心構え、考え方、行動指針等を理解し、自己の職業観確立のための一助とすると共に、思考力、判断力、実践力の向上を目指す。
明治大学大学院経営学研究科博士後期課程単位取得。専門は、管理会計、マネジメント・コントロール。国内大手金融機関、国内大手SIerにおいて事業企画、財務管理などを担当。2019年日本組織会計学会賞。
-
実務家教員

事業創造学部
渡辺 康英 准教授
WATANABE Yasuhide
担当科目
企業内実習Ⅰ
実際の企業現場で業務を体験することで信頼関係を築くことの重要性を理解し、また社会人としての身だしなみ・マナーについてもその能力と態度を身に付ける。
企業内実習Ⅲ
経営戦略や経営組織の理解、トップマネジメントの理解、会計・財務に関する理論を総合的に活用し、課題解決策を企画提案書にまとめ、プレゼンテーションを体験する。
ソーシャルデザインⅠ
地域社会におけるブランドの概念や目的を踏まえた基本的な着眼点や企画・構成等、どのように体系化されているのかを学修する。
ソーシャルデザインⅡ
地域の魅力を高めるための地域政策の在り方や最新の動向について学習する。また、公共政策の課題や問題点、あるべき方向性などについて考察する。
ソーシャルデザイン実習
地域社会が抱える問題を実際の事例にあてはめて、課題解決のための策定実習を行う。より優秀なプランについては自治体などへのプレゼンテーションも行う。
東京芸術大学美術学部建築科卒業、同大学院修士課程(環境造形デザイン)修了。(株)日本総合研究所でコンサルティングに従事。
-
実務家教員

事業創造学部
阿部 俊光 准教授
ABE Toshimitsu
担当科目
経営組織論
経営組織に関わる理論や概念の基礎について学ぶ。
情報リテラシー
大学での学習活動、卒業後の職業生活や社会生活において、情報の収集、分析や資料作成等知的活動を効率的、安全に進めるために不可欠な基本的な情報処理能力を身に付ける。
企業内実習Ⅲ
実習先企業の事業内容、社会的役割を理解し、業務現場の見学やヒアリング、実際の業務体験を通して自社の事業状況、自社の強みや弱みを把握し、業界事情の分析、市場の分析、競合他社の分析、社会環境の分析を踏まえて、実習先企業の抱える課題を認識し、課題の解決のための方策を考察する。
バブソン大学(MBA)修了。ヤンセンファーマ株式会社(ジョンソン・エンド・ジョンソンの医薬品部門)など外資系企業複数社に勤務し、グローバル企業のITマネジメント、人材管理・育成等を担当。
-

事業創造学部
松澤 孝紀 講師
MATSUZAWA Takatoshi
担当科目
企業内実習Ⅰ
実際の企業現場で業務を体験することで信頼関係を築くことの重要性を理解し、また社会人としての身だしなみ・マナーについてもその能力と態度を身に付ける。
資金調達の実践
現在の金融ファイナンスを理解するとともに、最新のマネジメント理論・事例を学修し、適正な経営を行うマインドと実践力を養成する。
青山学院大学、同大学院、跡見学園女子大学、同大学院、中央学院大学、日本大学、武蔵大学等で非常勤講師を歴任。専門はファイナンス。
-
実務家教員

事業創造学部
北野 奈々子 講師
KITANO Nanako
担当科目
キャリアデザインⅠ
人生や仕事において自分自身のなりたい姿を描くことについて理解し、個々の夢や目標を実現するための心のあり方や目標設定の仕方、振り返り、生じた問題への対処法など、目標に対して具体的にアプローチするための実践行動に関する知識と技法について学ぶ。
キャリアデザインⅡ
他者と協調・協働して行動できる態度や他者に方向性を示し、目標を達成するために動員できる能力を養成する。
キャリアデザインⅢ
学生が将来への目的意識を明確に持てるよう、職業観を涵養し、職業に関する知識を身に付け、自己の個性を理解したうえで主体的に進路を選択できる能力及び卒業後も自律・自立して学習できる態度を育成する。
企業内実習Ⅰ
国家資格キャリアコンサルタント。在職者・求職者のキャリア支援に従事。離職者向け受託職業訓練、生涯学習支援事業、子ども向け学習支援事業等の教育サービス事業を経営。
-
実務家教員

事業創造学部
庄司 義弘 講師
SHOJI Yoshihiro
担当科目
消費者行動論入門
「私たちがどのようにしてモノを買って使っているのか」を解き明かし、それぞれの人によって異なる多種多様な消費者行動を理解することを目的とする。
企業内実習Ⅱ
会社設立実習Ⅰで学修した事業計画、資金計画、経営(仮想)、決算、税務申告までの一連の流れの理解を踏まえ、学外での実際の会社設立を想定した具体的な計画を策定する。
商品開発実習
新潟大学大学院現代社会文化研究科博士後期課程修了。山形県内の地方銀行で中小企業の支援や個人のライフプラン支援に携わる。山形大学人文社会科学部非常勤講師、駿河台大学大学院総合政策研究科非常勤講師。学校法人山本学園惺山高等学校非常勤講師。
-
実務家教員

事業創造学部
市川 昌史 助教
ICHIKAWA Masashi
担当科目
企業内実習Ⅲ
実習先企業の事業内容、社会的役割を理解し、業務現場の見学やヒアリング、実際の業務体験を通して自社の事業状況、自社の強みや弱みを把握し、業界事情の 分析、市場の分析、競合他社の分析、社会環境の分析を踏まえて、実習先企業の抱える課題を認識し、課題の解決のための方策を考察する。
経営学の基礎
経営の基本的な事項といわれる、ひと、もの、金、情報の取り扱いを学ぶ。
現代産業論
鉄鋼、化学、自動車、流通、情報通信など、日本の代表的な産業を事例に挙げながら、これまでの環境変化や自己変革のプロセスについて学ぶ。
産業研究Ⅴ(観光)
基礎ゼミ
東洋大学国際地域学研究科修了。専門は観光で、観光地経営、DMOなどを研究。 ㈱JTBで仕入、商品企画、営業DX化や業務改善などの働き方改革を担当。 その後コンサル会社で中小企業の営業支援に従事。
-

事業創造学部
岡田 天太 助手
OKADA Tenta
学部3年次に指導教員と共に大学発ベンチャーを共同創業。明治大学経営学研究科修了。横浜市立大学博士後期課程在学中。産学連携活動及びその教育効果について研究を行っている。
-

情報学部
三上 喜貴 学部長/教授(副学長) 博士(政策・メディア)
MIKAMI Yoshiki
担当科目
トップランナー研究
産業界において先進の取り組みを実践している事例についての考察・研究を通じ、専門職業人としての心構え、考え方、行動指針等を理解し、自己の職業観確立のための一助とすると共に、思考力、判断力、実践力の向上を目指す。
国際文化と伝統
グローバルな視点を深め、異文化理解を進めるために国際文化交流の基礎となる日本と世界の伝統文化や生活文化について学ぶ。
臨地実務実習Ⅰ・Ⅱ
社会人・企業人に必要な姿勢や心構え、課題解決力をビジネスの現場で直接学び、業界のプロとして求められる実践力・応用力を身に付ける。
東京大学工学部計数工学科数理工コース卒業。通商産業省(現経済産業省)などで勤務。ハーバード大学国際問題研究所研究員、長岡技術科学大学理事・副学長、放送大学客員教授、日本MOT学会会長を歴任。
-
実務家教員
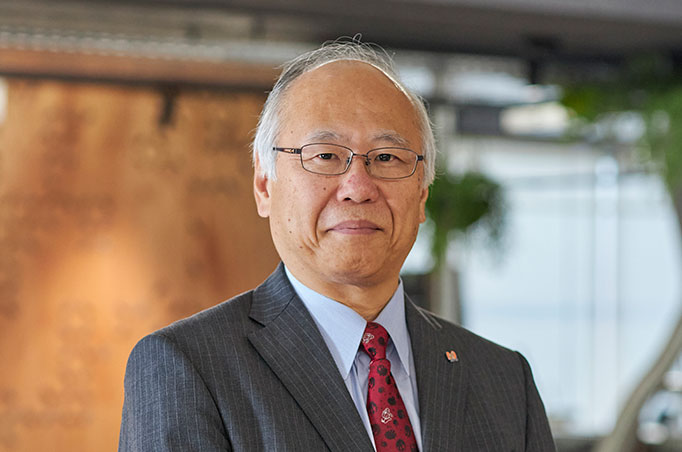
情報学部
磯西 徹明 教授
ISONISHI Tetsuaki
担当科目
コンピュータアーキテクチャ
アーキテクチャの意味を理解し、ノイマン型コンピュータの基本構成とその動作について学ぶ。
クラウド技術概論
クラウド・コンピューティングについて環境構築から開発運用のリードタイム短縮につながる技術の原理とその有効活用方法を学ぶ。
IoT実習
AI・IoT演習での学びを基に、より大規模なAI、IoTの構築・管理・検証を、実習を通して体系的に学ぶ。
新潟大学修士修了後、三菱電機入社。マサチューセッツ工科大学客員研究員、三菱電機インフォメーションシステムズ製造事業部長、中部支社長等を歴任。
-
実務家教員

情報学部
上野 衆太 教授 博士(工学)
UENO Shuta
担当科目
情報通信ネットワーク
情報通信ネットワークの技術体系と基本的構造、運用ポリシー、運用体系を学ぶ
システム開発技術
多数のコンピュータ、スマートデバイスで稼働するシステムの設計を、ネットワーク活用も含め学ぶ
分散型台帳技術
分散型台帳技術の特長や歴史を理解し、ブロックチェーンの仕組みや技術、分散型志向の設計と制作を実践的に学ぶ
日本電信電話(株)(NTT)通信研究所にて通信システム、無線システムの開発に携わる。
-

情報学部
後藤 幸功 教授 博士(情報科学)
GOTO Yukinori
担当科目
データ構造とアルゴリズム
計算機で扱われる基本的なデータ構造と、アルゴリズムの考え方や表現方法、代表的なアルゴリズムとその原理を学ぶ。
オペレーティングシステム
プロセス管理、入出力管理、記憶管理などオペレーティングシステムの基本的性能とその原理を学修し、情報システムの動作の全貌を理解する。
情報セキュリティ
社会の基盤となっている情報システムに対し、安心・安全な情報システムを実現するための原理や設計方法を学ぶ。
ネットワーク演習
インターネットの管理・運用体制や代表的なネットワーク機器の仕組み、運用法、セキュリティを理解する。
東京理科大学にて学術ネットワークの構築、JPNICの創設に従事。九州大学にて高速ネットワークを用いた大規模ビデオ配信システムの開発、ネットワーク運用に関する研究を行う。
-
実務家教員

情報学部
鈴木 源吾 教授 博士(工学)
SUZUKI Gengo
担当科目
データベースの基礎
データを組織化して一括管理するデータベースについて、その基本であるリレーショナルデータベースについて、データベースの管理、操作、設計、データ検索を高速化する基本技術を理解する。
確率論
確率の概念および、確率変数、確率変数の関数、近似理論など、確率の基礎を学修するとともに、その応用例についても触れることで、確率の必要性を理解するとともに、統計学及び、さらにその先に続く多様な情報学へ取り組むための素養とする。
統計学
膨大なデータを収集し分析/解析するデータサイエンスの基礎として、基本統計量、検定、推定理論など、記述統計学・推測統計学を学修し、さらに、回帰分析、多変量解析の基礎を学修する。
東北大学大学院で数学を専攻し,NTTにてデータベース・OSSなどのソフトウェア技術の研究開発に従事。工学博士。
-

情報学部
田代 秀一 教授 工学博士
TASHIRO Shuichi
担当科目
情報の基礎
「物質」、「エネルギー」に並ぶ第三の概念である「情報」について本質を理解し、人間社会とのかかわり、意義、課題について理解する。
情報産業論
情報の収集、整理、分析、加工、伝達等により価値を生み出す産業であることを解説し、情報産業の発展なしに人類の発展はないことについて理解する。
現代の科学技術
科学技術の成果は社会の隅々にまで浸透しており、生活のあらゆる場面で恩恵を受けていることについて理解する。いくつかの先端的科学技術をとりあげ、その概要や社会的意義、課題を学修する。
産業技術総合研究所、情報処理推進機構でインターネット、文字コード、データ構造などの国際標準化を推進。現ISO/IEC文字コード規格委員会議長。
-
実務家教員

情報学部
西川 昌宏 教授
NISHIKAWA Masahiro
担当科目
デザイン・シンキング概論
デザインに必要となる考え方や手法等を駆使して課題解決手法や新しい商品・サービスを生み出す手法であるデザイン・シンキングの考え方、課題を解決するための手法やプロセス、チームでの課題解決に必要なチームワークやコミュニケーション力、ディベート力の必要性を学ぶ。
デザイン・シンキング実習Ⅰ・Ⅱ
課題解決の各種手法を実践するため、少人数グループを作り、調査・情報収集を実施し、課題を見つけ、解決策を検討・実施評価するデザイン・シンキング手法を、特にその後の課題解決案の検討を重視して実施する。
ユーザエクスペリエンス
ユーザエクスペリエンスとは、製品やサービスの利用を通じてユーザーが得る経験であり、よいユーザエクスペリエンスを達成するための理論とプロセスや手法に関する知識について学ぶ。
早稲田大学法学部卒業。NECに入社、広告宣伝、マーケティング業務に従事。その後、デザイン戦略およびデザイン・シンキングの全社活用推進を担当。
-
実務家教員

情報学部
平川 秀樹 教授 博士(情報理工学)
HIRAKAWA Hideki
担当科目
マシンラーニング
マシンラーニング(機械学習)とは、人工知能における研究課題の一つで、人間が自然に行っている学習能力と同様の機能を、コンピュータで実現しようとする技術・手法であることについて理解するとともに、AI技術の一つであるマシンラーニングについて、演習を通して学修する。
微分積分
専門分野への応用に備えて、微分積分法の基本事項を習得する。数列や関数の極限の概念に習熟し、1変数関数の微分積分、多変数関数の偏微分、重積分と微分方程式について、具体的な計算が出来ることを目指す。
情報科学基礎
情報をどのように表現し、伝送するか。情報を処理するとはどういうことか。これらを体系化した学問である「情報理論」と「離散数学」の基礎を学ぶ。
(株)東芝の研究所で自然言語処理研究に従事、製品開発/市場開拓に展開。マサチューセッツ工科大学、東芝ロンドン拠点など海外勤務。
-
実務家教員

情報学部
藤巻 佐和子 教授
FUJIMAKI Sawako
東北大学文学部(社会学科)、早稲田大学ビジネススクール修了(MBA)。日本電信電話株式会社、NTTコミュニケーションズ、NTTドコモなどNTTグループ企業にて、新規事業開発、AIサービスの企画などに従事。
-
実務家教員

情報学部
堀川 桂太郎 教授
HORIKAWA Keitarou
担当科目
AI実習
AIの要素技術について実社会において生成された技術を活用し、プログラムやアプリを作成する技術・知識を学ぶ
プログラミングⅠ
データ構造と制御に係るプログラミングの基礎と必要な各種操作を学ぶ
データ構造とアルゴリズム
計算機で扱われる基本的なデータ構造と、アルゴリズムの考え方や表現方法、代表的なアルゴリズムとその原理を学ぶ
日本電信電話(株)(NTT)の研究所にてソフトウェアにかかわる研究・開発・運用・ビジネス・マネジメントを実践。
-

情報学部
小野山 博之 准教授 博士(農学)
ONOYAMA Hiroyuki
担当科目
サイバーフィジカルシステム基礎
IoTデバイスに関する基礎知識やデバイスとワンボードマイコンとの接続の基礎技術、フィードバック制御及び制御理論の基礎、画像処理と表示技術の基礎を習得する。
ハードウェア設計
コンピュータやスマートデバイス、各種センサー類を活用し、求められる機能・性能を実現するハードウェアの設計能力を学ぶ。また、ロボットやIoTの実践・実習でも必要となる3Dスキャナ・3Dプリンター等の機器の利活用技法についても学ぶ。
ロボティクス実習
単腕ロボットやヒューマノイド型ロボットの運動制御、およびそのためのシステムインテグレーションを修得する。また、構造体・動力伝達部位などを構成するアクチュエータ・モーターの原理・機構や制御プログラミングなどについて学ぶ。
京都大学大学院農学研究科地域環境科学専攻の博士課程修了後、立命館大学助教、同大学准教授を経て現在に至る。農業情報工学および農業機械のロボット化に関する研究に従事。
-
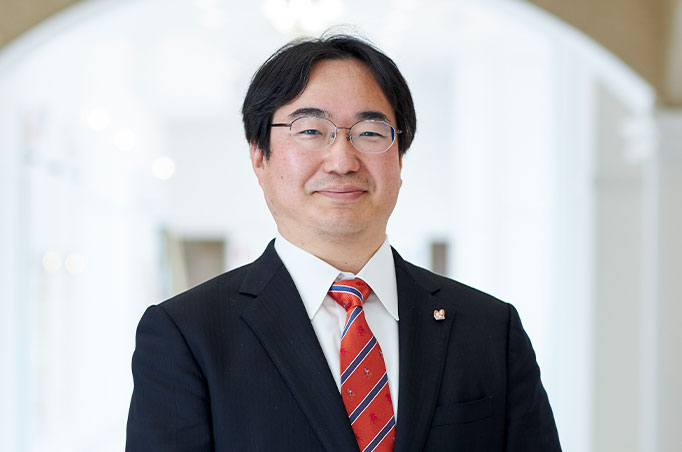
情報学部
柄沢 直之 准教授 博士(工学)
KARASAWA Naoyuki
担当科目
データベースの基礎
データベース管理システムの目的や機能と、操作・設計の基本技術を学ぶ
プログラミングⅠ・Ⅱ
データ構造と制御に係るプログラミングの基礎と必要な各種操作を学ぶ
ICT演習(応用情報)
情報技術を活用した戦略の立案、システムの構築、運用サービスを学ぶ
新潟大学工学部情報工学科にて、移動情報ネットワークや情報通信ネットワークの制御と性能評価に関する研究に従事。
-
実務家教員

情報学部
江口 将史 講師
EGUCHI Masashi
担当科目
没入型コンピューティング
ユーザーの五感を含む感覚を刺激する技術について理解し、仮想現実(VR)実装技術などを体験を通じて学ぶ。
没入型コンピューティング実習
実際の業務・エンタテインメントでの利用を前提に、ユーザーの心理的・肉体的負担なども考慮したコンテンツの作成を行う。
米国サンディエゴ州立大学修士。日本マイクロソフト株式会社、株式会社ホロラボを経て、2022年ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン株式会社で勤務。xRソリューション開発のプロジェクトマネージャー職として、グローバル チームと連携した顧客課題解決案件に従事。
-
実務家教員

情報学部
渋谷 修太 講師
SHIBUYA Shuta
担当科目
マーケティング実践
マーケティングのベストプラクティス、マーケティング戦略に取り組む姿勢について理解する。
ソーシャルデザイン実習
地域社会が抱える課題を解決するための技法について、プラン策定実習を通じて学ぶ。
国立長岡工業高等専門学校卒業。筑波大学編入学。グリー株式会社にてマーケティングに従事。2011年11月フラー株式会社創業、代表取締役CEO就任。2016年、世界有数の経済誌Forbesにより30歳未満の重要人物「30アンダー30」に選出。
-
実務家教員

情報学部
西川 浩平 講師
NISHIKAWA Kohei
担当科目
API実習
プログラム開発の生産性を高めるAPI技術について、実習を通じて体系的に学ぶ。
クラウドベーシック&マーケティング
クラウドコンピューティングサービスを活用したアプリケーションシステムの開発手法を学ぶ。
クラウドプラットフォーム実習Ⅰ・Ⅱ
クラウド技術概論、クラウドベーシック&マーケティングで学んだ知識や技術を基に、サービスモデルを設計・構築する。
金沢工業大学大学院工学研究科修了。GBS(JBグループ)等に勤務。クラウド分野で経営企画、営業、開発、AI開発研修講師に従事。2017-2020 IBM Champion選出。
-

情報学部
PANN YU MON 助教 博士(工学)
PANN YU MON
担当科目
ネットワークプログラミング実習
実習を通し、ネットワーク上で情報をやりとりするプログラムに関する知識と技術を学ぶ。
ICT演習(基本情報)
各分野のシステムの企画や要件定義、開発プロセスを実践的に学び、利活用の技法を理解する。
ICT演習(ハードウェア/ソフトウェア)
IoTの企画・開発・利用に必要な技術と知識を、体系的に学修する。
2011年よりミャンマーコンピュータ連合、ナイングループホールディング(株)、Flymya.com などで講師、MIS部門長、ITプロダクトマネージャーを務める。
-

情報学部
𠮷田 貴裕 助教
YOSHIDA Takahiro
新潟大学大学院にて物理学を専攻し、博士(理学)の学位を取得。新潟医療技術専門学校において非常勤講師として教育に携わる。新潟大学理学部にて特任助教として研究に従事。専門は素粒子理論、特に初期宇宙における物質・反物質非対称性の問題やニュートリノ物理。
-

情報学部
清水 勇介 助手
SHIMIZU Yusuke
新潟大学にて博士(理学)の学位を取得。マックス・プランク原子核物理学研究所日本学術振興会海外特別研究員、高等科学院研究員、広島大学日本学術振興会特別研究員、広島大学助教、新潟大学特任助教を経て本学に着任。専門は素粒子論、特に素粒子の世代構造を探るフレーバー物理やニュートリノ物理などの現象論。
-

アニメ・マンガ学部
堀越 謙三 学部長/教授
HORIKOSHI Kenzo
担当科目
企画開発概論
アニメ・マンガ・映画作品等を作りたい、描きたい話またはシーンがあるとき、いくつかのアイデアからどれを選び、どう調査・開発していくか、その企画開発の手順を各自が実際にプロットを書き上げるなかで体験する。
企画プロデュース演習
10分程度の短編映画のシナリオを全員が書き、2~3本の撮影稿を学生同士のディスカッションによって決定。その企画のブラッシュアップと撮影に向けたロケーション調査・キャスティングなどを行う
企画プロデュース概論
自分が何を作りたいのか、何をしたいのかを俯瞰し、問題点を整理し、そのアイデアにかたちを与えて企画に昇華させ、実現していくロードマップを描く。
物語芸術workshopⅠ
演劇集団を招聘し、2グループの分かれて短い演劇作品を創作、学内で発表公演を行うことで、集団創作のなかでのコミュニケ―ション能力を鍛錬する。
表象芸術論
アニメ・マンガの視覚的構成要素としての、服装や化粧の社会学的ドレスコード、所作、そして絵画的背景論・空間論、建築・室内空間・工業製品などの社会性・記号性など、教養と理解を深める。
東京藝術大学名誉教授。1982年ミニシアターの草分け「ユーロスペース」、1997年「映画美学校」設立。2005年東京藝術大学映像研究科を立ち上げる。外国映画を中心に「スモーク」「ポンヌフの恋人」など約30本を製作。2014年からは「渋谷らくご」「浪曲映画祭」など大衆芸能の伝承に尽力。(独)国立美術館運営委員等歴任。映画ペンクラブ賞、川喜多賞、仏・文化功労勲章シュヴァリエ受勲。
アニメーション分野
-
実務家教員

アニメ・マンガ学部
西村 潤子 准教授
NISHIMURA Junko
担当科目
アニメ表現基礎
アニメ業界およびアニメーターという職種について、概要と基礎知識を学ぶ。
作画演習
アニメーション制作現場で必要となる知識・技術を修得し、新人アニメーターのワークフローを学ぶことで、臨地実務実習への準備を整える。就活で通用する動画専用ポートフォリオを作成する。
デジタルペイント実務
実習先企業での業務体験を通じ、専攻分野に必要なデジタルペイントの種類や作業を理解する。
プロダクション I.Gにて、30年近く動画検査の仕事をする。代表作は、劇場作品「イノセンス」、TVアニメーション「よんでますよ、アザゼルさん」。
-
実務家教員

アニメ・マンガ学部
深井 利行 教授
HUKAI Toshiyuki
担当科目
アニメ制作実務Ⅰ・Ⅱ
業界の実務(求められる技術と品質の高さ)を理解する。同時に、実務を進めるために必要なビジネスマナーとコミュニケーションスキルを磨く。
アニメ表現基礎
アニメ業界およびアニメーターという職種について、概要と基礎知識を学ぶ。
デジタルアニメ実習
アニメーション制作支援ソフトの基本操作から完成までの実作業を、順を追って学修する 。
作画演習
人間はなぜそう動くのかを観察し、その動きに物理的整合性はあるのか考えるといった習慣をつけ、柔軟な発想で動きと演技を描き、世界に通用する技術を習得する。
運動表現理論
イメージした世界観にあたかも実際に存在しているかのようなキャラクターを描く力を身に付ける為、動きに関する物理的な法則を描き出す表現方法について学修する。
東京ムービー、ウォルト・ディズニー・アニメーションスタジオ・ジャパン、手塚プロダクション、ブレインズ・ベースなどで活動。主な仕事は『ムーラン2』ユニット・プロデューサー『ASTRO BOY 鉄腕アトム 10万光年の来訪者・IGZA』プロデューサー、文化庁委託事業若手アニメーター等人材育成事業ヒアリング委員(2010-2016年度)。
-
実務家教員
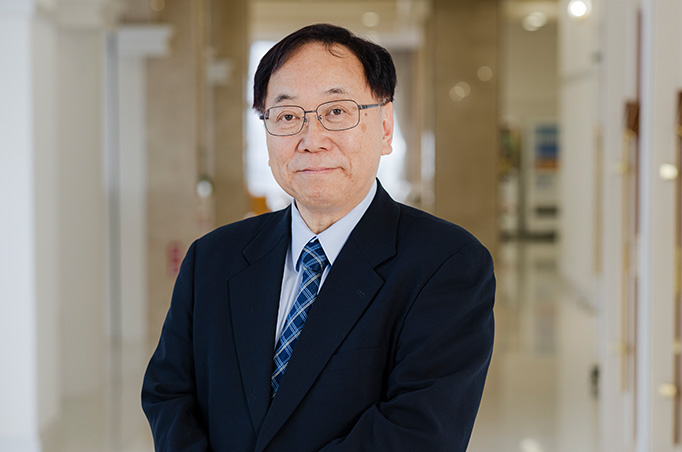
アニメ・マンガ学部
渡部 英雄 教授
WATANABE Hideo
担当科目
アニメ制作実習
アニメ制作工程演習
アニメ基礎演習Ⅰ・Ⅱ
演出表現論
北海道札幌生まれ。アニメ業界で監督・演出・原画を担当。絵コンテ、映像論、アニメ制作実習を教えている。現在は3DCGアニメ制作やVR制作の研究、アニメの現場で演出を担当している。過去に、機動戦士Zガンダムの絵コンテ、北斗の拳2の演出、夢戦士ウイングマンのOP・EDの演出、新世紀エヴァンゲリオンの原画などを多数担当。著書に『アニメ研究入門【応用編】アニメを究める11のコツ』現代書館(共著)。
-
実務家教員

アニメ・マンガ学部
室井 ふみえ 教授
MUROI Fumie
担当科目
演出表現論
より効果的な演出について、アニメの設計図ともいうべき「絵コンテ」を通して学修する。また、観客が混乱せず理解しやすいカット割りについて学修する。
アニメゼミⅠ・Ⅱ
内定取得を目的とした、徹底した個別指導による進路相談、制作会社調査研究などをおこなう。
アニメ制作実務Ⅰ・Ⅱ
業界の実務(求められる技術と品質の高さ)を理解する。同時に、実務を進めるために必要なビジネスマナーとコミュニケーションスキルを磨く。
総合制作研究実習Ⅰ・Ⅱ
学修した知識・技能を統合して作品制作や研究論文を完成させ、発表会でプレゼンテーションを行う
アニメーションクリエイター、イラストレーター。元神戸芸術工科大学准教授。葦プロダクションにて動画としてアニメーターを開始する。「幽遊白書」で作画監督デビュー、TV「アクエリアンエイジ」で総作画監督、「るろうに剣心」でキャラクターデザイン「コレクター・ユイ」でオリジナルキャラクターをデザイン。「BlackLagoon」で演出、作画監督、OVA「炎の蜃気楼」で監督、作画監督。はじめの一歩では脚本も担当。劇場版「LIP×LIP-FILM&LIVEこの世界の楽しみ方」で映画監督するなど、活動は多岐にわたる。絵本の挿絵やゲームのキャラクターデザインも手掛ける。
マンガ分野
-
実務家教員

アニメ・マンガ学部
belne 教授
belne
担当科目
マンガ脚本演習
複数名のマンガ教員による徹底した少人数制個別指導が行われる。テーマのあるショートマンガ3本、オリジナルマンガ1本で、オリジナル8ページ作品を完成させる。
マンガ脚本実習
ストーリーマンガの商業誌応募基本単位である16ページまたは24ページのオリジナル作品と、商業的ニーズの高いエッセイ実用マンガ4ページ 1本を制作する。
マンガ表現演習
8ページのテーマショート課題三本のネームを作成するにあたり、自発的な講師とのディスカッションをくり返すことで、マンガ力が質、量ともに強化されていくことを目指す
マンガ表現実習
プロクオリティにこだわり、外部発信できる水準の作品に仕上げることを目指す。作品は印刷冊子・Webなどで発表する。
マンガ表現基礎
同じコンテンツ産業のなかで重なり合う隣接分野であるアニメ・キャラクターデザインを意識した上で、マンガという業界、マンガ家という職種についての概要と基礎知識を学ぶ。
マンガ基礎演習Ⅰ
ネームで物語をデザインする発想法、プロット作り、読み手を惹きつけるキャラクター設定、ネーム構成方法、下描きへの準備を実作で学ぶ。
マンガ基礎演習Ⅱ
教員とのディスカッションをくり返すことで、物語をブラッシュアップしてゆく方法を身につける。
マンガ家。1976年デビュー。代表作「異端文書」朝日ソノラマ刊。京都精華大学マンガ学部で14年間講師を務める。共著に「マンガで読み解くマンガ教育 (京都精華大SEIKAマンガ教育研究プロジェクト)」週刊少年マガジン「ゴッドハンド輝(山本航暉)」の構成監修原作協力(筆名天碕莞爾)。新潟マンガ大賞二次審査員。日本マンガ学会・日本漫画家協会会員。第25回文化庁メディア芸術祭功労賞受賞。
-
実務家教員

アニメ・マンガ学部
日高 トモキチ 講師
HIDAKA Tomokichi
担当科目
マンガ脚本実習
ストーリーマンガの商業誌応募基本単位である16ページまたは24ページのオリジナル作品と、商業的ニーズの高いエッセイ実用マンガ4ページ 1本を制作する。
マンガ表現実習
プロクオリティにこだわり、外部発信できる水準の作品に仕上げることを目指す。作品は印刷冊子・Webなどで発表する。
イラスト実務実習(企業内実習)
実習先企業でイラスト作成にまつわる実務に携わることで、顧客要求に応える創造力と、制作進行に関わる基礎的な管理能力を身に付ける。
マンガ家・イラストレーター・文筆家。元京都精華大学マンガ学部講師。著書に「レオノーラの卵」「ダーウィンの覗き穴」「水族館で働くことになりました」「原色ひまつぶし図鑑」「トーキョー博物誌」「里山奇談」ほか、小説・エッセイの挿画、ゲームアイデア協力等多数。早稲田大学漫画研究会出身。日本漫画家協会・日本SF作家クラブ会員。
-
実務家教員

アニメ・マンガ学部
高山 瑞穂 講師
TAKAYAMA Mizuho
担当科目
デジタルマンガ表現論
マンガ原稿の作成から、ツールの基本操作、フルデジタル作業でのペンワークなど、デジタルマンガ制作の基本スキルとなる、制作ソフトの基礎技法を学ぶ。
マンガゼミ
前期、後期合計で32ページ以上のマンガ作品を制作。学内展示とゼミ展、発表、総評も行う。
キャラクターイラスト・マンガ実務
キャラクターイラスト関連実務に携わることで技術を研鑽し、計画的に学修に取り組む姿勢を身に付ける。
マンガ家。アニメーターとして「Zガンダム」「ボトムズ」などに参加。マンガ家に転身後は「覇王マガジン」「コミックボンボン」などでアニメやゲームなどのコミカライズ作品を多数手がける。代表作は「ガンダム外伝」「マクロスダイナマイト7」「ガンダムSEED」「ガンダムSEED DESTINY」「ガンダムALIVE」など。元京都精華大学講師。
キャラクターデザイン分野
-
実務家教員
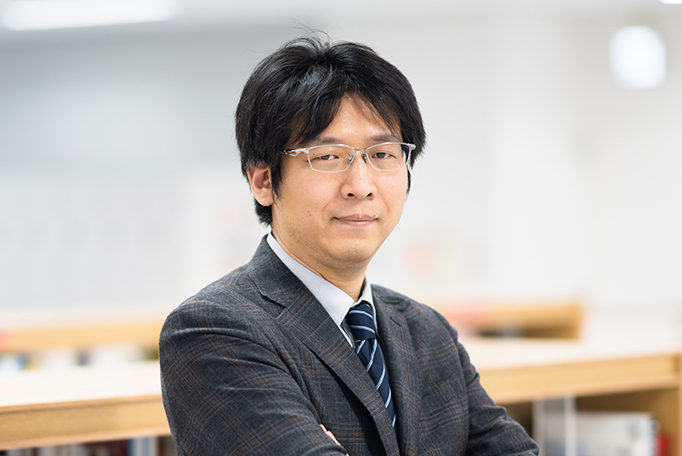
アニメ・マンガ学部
瓜生 幸夫 講師
URYU Sachio
担当科目
キャラクターデザイン表現基礎
同じコンテンツ産業のなかで重なり合う隣接分野であるアニメ・マンガを意識した上で、キャラクターデザイン業界、キャラクターデザイナーという職種についての概要と基礎知識を学ぶ。
キャラクターデザイン基礎演習Ⅰ・Ⅱ
アイデアを幾通りにも展開させブラッシュアップしていく柔軟な対応力を学修し、資料の探し方、取材方法、技術的な試行錯誤の定石手法など、ケースに応じた問題解決方法を修得する。
キャラクターコンテンツ企画演習
企画書を作成し、キャラクターデザインの習作、デジタルイラストの作成、商品規格に合わせる画像処理作業を経て、Webでの商品販売まで一貫して行う。
キャラクターデザイン演習
キャラクター創作におけるプロの方法論と、それを実際に絵として描き出す技術を学ぶ。
キャラクターデザイン実習
プレゼンや就活など、すべてのシーンで重要となる、ポータルキャラクターやWebゲーム、ポスター、挿絵などについても基本的な考え方からノウハウまで実践的に学修する。
キャラクターデザインゼミⅠ・Ⅱ
企業が必要とするクリエイター像、スキルについて各自調査研究し、プレゼンおよびグループディスカッションをおこなう。
イラスト実務実習
ここまでの学修で修得した創作に必要な知識、理論、技術を活用し、実務に則した技術を修得する中で、「分野を支える基礎的な知識、技能」の実証を行うために、実際に取引されている実務に沿った創作に取り組む事で、以降に続く臨地実務実習の準備を行う。
キャラクターイラスト・マンガ実務Ⅰ・Ⅱ
キャラクターイラストやマンガを活用した実務に携わることで、学んできた創作技術や表現力が、様々の業種・業態・製品に対し、広範囲に活用されていることを理解し、学修してきた創作技術、表現力を生活の糧とするための手法について学修する。
ゲーム開発専門の2Dデザイナー。キャラクターデザイン、コンセプトデザイン、UIUXデザイン、演出デザイン、アートディレクターなど2D全般のデザインに幅広く携わる。またサービス開発やesportsチームの運営も行っている。
-
実務家教員

アニメ・マンガ学部
ヨシカワ ゴエモン 教授
YOSHIKAWA Goemon
担当科目
ライフドローイング理論および演習
人体の構造を観察・表現する方法を学び、アニメ・マンガ・キャラクターデザイン分野の絵描きとして、基礎練習の段階で絵はどのように描くべきかといった方法を理解・修得する。
ライフドローイング演習
人体を立体としてとらえる方法を学び、リアリティをもって表現できる描画力を身につける。
立体デザイン
美術家。店舗・イベント・出版・広告などのアートワークで活動。「ソラヲトブ・・・フシギ・・・」をテーマにスポンジや担当科目 ライフドローイング理論および演習 ライフドローイング演習 立体デザイン 金属のオブジェ、イラストやミクストメディアの平面作品を制作。ゼンマイや電気で「動き・音・光」を盛り込んだオブジェによる空間作りも手がける。京都芸術大学マンガ学科客員教授。現代日本美術会参与。
-
実務家教員

アニメ・マンガ学部
工藤 遥 助教
KUDO Haruka
担当科目
イラスト実務実習
キャラクターイラスト・マンガ実務Ⅰ・Ⅱ
キャラクターイラスト・マンガ実務
キャラクターコンテンツ企画演習
キャラクターデザイン演習
キャラクターデザイン表現基礎
キャラクターデザインゼミⅠ・Ⅱ
キャラクターデザイン基礎演習Ⅰ・Ⅱ
総合制作研究実習Ⅰ・Ⅱ
デザイナー・イラストレーター。博士(美術)。デザイン会社に勤務後、フリーランスとして主にキャラクタートイ業界でのデザインに携わる。女児向け玩具や食玩フィギュアのプロダクトデザイン、ラインナップスケッチ、イラスト、ロゴデザイン、パッケージデザイン等を手がけている。日本デザイン学会会員。
脚本・プロデュース領域
-
実務家教員

アニメ・マンガ学部
村井 さだゆき 教授
MURAI Sadayuki
担当科目
文学
創作の基礎となる文学の基本的な教養を身につけ、創ることの意味について深く考察する思考の習慣を習得する。
物語記号学
実際に脚本がメッセージを伝える原理を、記号学の考え方に基づいて学ぶ。
脚本概論
物語の基本原理を紐解き、20世紀の映画誕生に至るまでの創作技法の変遷を概観。映像制作の現場で必要となる脚本についての基本的知識を身につける。
近代世界観研究
近年のアニメ制作の現場で、創作の最も重要な要素の一つとされる「世界観」について、特に近代史の視点から探究する
脚本家。第6回フジテレビヤングシナリオ大賞受賞。映画美学校にて脚本コース講師を務める。代表作に映画「PERFECT BLUE」「千年女優」(今敏監督)、「スチームボーイ」「蟲師」(大友克洋監督)の脚本や、TVアニメ「魍魎の匣」「夏目友人帳」「シドニアの騎士」「十二大戦」などのシリーズ構成があり、実写、アニメを問わず幅広い創作活動を続ける。
-
実務家教員

アニメ・マンガ学部
成田 兵衛 教授
NARITA Hyoe
担当科目
コンテンツビジネス概論
アニメを中心にキャラクタービジネス、マンガ、映画などコンテンツに関わる製作・流通のビジネス構造の基本概念を学ぶ。
マンガ産業論
産業的視点から、非常に多様性のあるマンガというコンテンツを取り巻く状況を概観し、国内外のマンガ市場における収益構造モデルを学修する。
1988年より小学館に9年在籍。女性誌やマンガ雑誌編集を経て、1996年小学館・集英社の米国子会社VIZ Media(サンフランシスコ)上席副社長。2002年北米版SHONEN JUMPを創刊、初代編集長に。2012年―2017年VIZ Media Europe(パリ、ベルリン、ローザンヌ)President。2014年―2017年在仏日本商工会議所・副会頭。2019年より(株)ヒューモニー代表取締役、(株)ファンタジスタ取締役会長。
アニメ・マンガ研究領域
-

アニメ・マンガ学部
木村 智哉 准教授
KIMURA Tomoya
担当科目
アニメ概論
アニメーションの成り立ちや産業構造、表現技法等を多角的に概観し、関連する周辺領域の文化表現にも関心を広げることで、アニメーションに関する包括的なものの見方と、学術的な思考方法を修得する。
アニメ産業論
アニメーション関連メディア産業の基礎知識を踏まえ、アニメーション産業の構造を学ぶ。
アニメ作家研究
さまざまなアニメ作家と作品について知り、具体的な知識を修得するとともに、鑑賞体験の成果を言語化し、批評・分析する能力を身につける。
アニメーション産業史を専門に研究。千葉大学大学院で博士号取得後、首都圏の複数の大学で、非常勤講師としてアニメーションや映画、大衆文化等についての講義を担当。また、早稲田大学演劇博物館で研究助手を、現・国立映画アーカイブでは客員研究員を務めた。単著『東映動画史論 経営と創造の底流』で日本アニメーション学会賞2021を受賞。
-

アニメ・マンガ学部
横山 昌吾 准教授
YOKOYAMA Shogo
担当科目
映像音響概論
音響の基礎知識とワークフロー、音響表現について理解し、スキルを習得する。
物語芸術workshopⅡ(実写映画制作)
アニメーションの表現に多大な影響を与えてきた映画の技術と映画的表現を学ぶため、役者を使った実写映画の制作を行う。
ポストプロダクション実習
映像制作におけるポストプロダクションのワークフローを理解し、ソフトの基礎知識と技術を習得する。
映像編集者としてアッバス・キアロスタミ監督作品「Like Someone in Love」、アミール・ナデリ監督「CUT」など国内外の作品を多数担当。東京藝術大学大学院映像研究科では、教員として国際プロジェクトを主導する。ASEAN諸国を対象に開催する国際映画制作ワークショップのディレクターを長年にわたり務めている。映像メディア学博士。
-

アニメ・マンガ学部
雑賀 忠宏 講師
SAIKA Tadahiro
担当科目
マンガ概論
マンガの表現特徴や多様性、メディアの変遷に伴う産業構造の変化などの基本的な知識を学び、分析・研究視点をもってマンガへ向き合う姿勢を身につける。
マンガ史
具体的な資料を参照しながら、戦後の日本におけるマンガという表現領域の歴史的展開を学ぶことで、現代におけるマンガ作品の意義や位置づけを把握し、言語化できる能力を身に付ける。
サブカルチャー論
メディア研究・文化研究の視点から、サブカルチャーとしてのマンガについて学ぶ。
社会学者・マンガ研究者。博士(学術)。複数の大学でマンガ史・大衆文化論等の講義を担当しつつ、京都精華大学国際マンガ研究センター委託研究員(2014~2020)として京都国際マンガミュージアムのコンテンツ制作などに従事。研究テーマは日本における「マンガを描くこと」の言説史など。
-

アニメ・マンガ学部
青木 健一 助教
AOKI Kenichi
担当科目
アニメ・マンガによる地域振興事例研究および演習
アニメ・マンガで地域振興を推進する行政区の取り組みをフィールドワーク、ロケハン、取材を通して調査・研究し、将来的に新潟の地域振興のために必要なことは何か提案をまとめ、プレゼンテーションを行う。
物語芸術workshopⅠ(演劇制作)
演劇集団を招聘し、2グループの分かれて短い演劇作品を創作、学内で発表公演を行うことで、集団創作のなかでのコミュニケ―ション能力を鍛錬する。
文化啓発施設運営実務
臨地実務実習先施設の目的、実習内容を理解し、知識・技術向上のため施設運営の実務を学ぶ。
専門は造形分野の基礎教育。1999年6月より「日本アニメ・マンガ専門学校」の開学業務に携り、開学後は教員として勤務。その後2007年「国際映像メディア専門学校」の開学業務を担当。映画、俳優の分野を専門とする「国際映像メディア専門学校」開学後は教務部長として教育課程の設計・運営に担当し、最終的に学校長を務めた。
出版・編集/3DCG
-
実務家教員

アニメ・マンガ学部
野上 勇人 准教授
NOGAMI Hayato
担当科目
キャリアデザインⅢ
学生が将来への目的意識を明確に持てるよう、職業観を涵養し、職業に関する知識を身に付け、自己の個性を理解したうえで主体的に進路を選択できる能力及び卒業後も自律・自立して学習できる態度を育成する。
パブリッシング実習Ⅰ・Ⅱ
ここまで学修してきた情報の伝達と訴求に関する理解と、ツールを用いた制作技術を総合し、ポートフォリオとして通用する水準の電子出版、およびアナログでの作品誌を制作し、マンガ冊子、イラスト集、キャラクター設定集など、選択した職業分野に応じ、自らをPRする作品誌を企画し、リリースするまでの工程を総合的に学修する。
印刷・広告実習Ⅰ・Ⅱ
学内で学修させる事が困難な企業内の品質管理体制に着目し、自分の立ち位置の理解を深めると共に、制作物の品質管理の仕組みを観察し、実務の一端を担う責任感を涵養すると共に、状況によって変化する様々な工程の中で担当する業務内容から、業務フロー全体の構造的な理解を深める。
総合制作研究実習Ⅰ・Ⅱ
アニメ・マンガ・キャラクターデザイン分野の専門職業人として、実践的かつ応用的な能力を総合的に高めるため、職業専門科目を中心に身に付けた知識・技能を統合した総合的な実習を行う。
編集者、ライター。1975年生まれ、埼玉県出身。1999年に中央大学法学部法律学科卒業。大学卒業後、広告系編集制作会社から編集キャリアをスタートさせ、出版系編集制作会社に移る。以後、実業之日本社、イーブックイニシアティブジャパン、ワークスコーポレーション(現・ボーンデジタル)、SHIBUYA PUBLISHING & BOOKSELLERS(SPBS)、ソシム、秋水社など出版関連会社10社近くに所属。それぞれの会社で広告・販促ツール・雑誌・書籍・電子書籍など、さまざまな出版コンテンツの編集を手がける。実用・ビジネス・デザイン・PC・コミックなど、媒体ジャンルも幅広い。イーブックでは2004年に『北斗の拳』の電子化に携わり、電子書籍として当時日本初のシリーズ10万部を達成した。2001年~2002年にはフランス・パリに遊学、日本食レストラン「AZABU」の新規オープンに参加。2012年8月、合同会社CRAZY(編集制作会社)を設立、業務執行社員に就任。2015年には東北芸術工科大学芸術学部文芸学科に着任し、講師、准教授を歴任。日本文化デザインフォーラム会員。
-
実務家教員

アニメ・マンガ学部
日髙 千秋 講師
HIDAKA Chiaki
担当科目
3DCGソフト演習Ⅰ・Ⅱ
イラスト実務実習
キャラクターイラスト・マンガ実務Ⅰ・Ⅱ
キャラクターデザインゼミⅠ・Ⅱ
総合制作研究実習Ⅰ・Ⅱ
3DCGクリエイター。2013年からフリーランスとして活動し、主にディレクション、3DCGアニメーション業務に携わる。ゲーム・アニメ・映像など、ジャンルを問わず幅広く活動。大学や専門学校にて3DCGに関する教育にも携わる。
教育助手
-

アニメ・マンガ学部
蕗谷 雄輝 助手
FUKIYA Yuki
日本文学研究者。専門は平安文学(特に『源氏物語』)。立教大学大学院博士課程修了。博士(文学)。複数の中高一貫校・大学で非常勤講師として教育に携わる。共著に『源氏物語〈読み〉の交響Ⅲ』(新典社、2020年)。
-

アニメ・マンガ学部
今井 理子 助手
IMAI Riko
武蔵野美術大学油絵専攻卒業。東京藝術大学大学院映像研究科アニメーション専攻修了。2Dアニメーションやインスタレーション作品の他、漫画やイラスト等のアートブック制作を行う。
-

アニメ・マンガ学部
岩城 つくし 助手
IWAKI Tsukushi
京都精華大学マンガ学部マンガ学科ストーリーマンガコース卒業。主にCLIP STUDIO PAINTでマンガ制作を行う。
-

アニメ・マンガ学部
小針 莉緒奈 助手
KOBARI Riona
主にイラスト、ポスターデザイン制作などを行っている。長岡造形大学在学中、アートプロジェクト「長岡芸術工事中」の運営の一員として活動し現在に至る。JAGDA国際学生ポスターアワード2019入選。
-

アニメ・マンガ学部
境 佑莉 助手
SAKAI Yuri
高岡工芸高等学校デザイン・絵画科卒業。大阪芸術大学デザイン学科デジタルアーツコース卒業。デジタル作画ツールを学び、特にLive2dを使用した2Dアニメーション作品を中心に制作を行う。
-

アニメ・マンガ学部
鈴木 潤 助手
SUZUKI Jun
新潟大学大学院博士後期課程修了。博士(学術)。新潟県内の公立高校で講師として勤務しながら、新潟大学アニメ・アーカイブ研究センターでアニメ中間素材のデジタルアーカイブ化作業に従事。共著に『幽霊の歴史文化学』(思文閣出版、2019年)など。
日本を代表する客員教授
長井 龍雪
アニメーション監督、演出家
第62回芸選奨「メディア芸術部門」文部科学省大臣新人賞受賞
【主な作品】「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」「心が叫びたがってるんだ。」「空の青さを知る人よ」
田中 将賀
アニメーター、キャラクターデザイナー、イラストレーター、作画監督
【主な作品】「君の名は」「天気の子」「シン・エヴァンゲリオン劇場版」「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」「心が叫びたがってるんだ。」「空の青さを知る人よ」
小林 浩康
株式会社カラー 取締役
株式会社プロジェクトスタジオ Q 代表取締役社長
【主な作品】「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序CGI 監督、デザインワークス」「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破CGI 監督、デザインワークス」「劇場版 機動戦士ガンダム00 -A wakening of the Trailblazer-モニターグラフィックス」「攻殻機動隊 S.A.C. SOLID STATE SOCIETY 3D - CG 協力」「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q CGI 監督、デザインワークス」「宇宙戦艦ヤマト2199 星巡る方舟モニターグラフィックス」「シン・エヴァンゲリオン劇場版CGI 監督」


